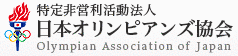- トップページ
- オリンピアンインタビュー
- 第20回 結城昭二さん
【代表落選の苦い経験】
元川悦子(以下、元川):結城さんは、男子バスケットボールでオリンピックに出られた最後の世代になってしまっているわけですが…
結城昭二(以下、結城):最後じゃないですよ、まだこれから、可能性があります。
元川:それはもちろんです。ただ現状では最後に出られた世代なので、オリンピックに出られた当時のレベルはどうだったかとか、その後のバスケットボール界がどうかということを伺いたいと思います。モントリオール大会の時代の日本男子バスケットはどんな状況だったのでしょうか。
結城:東京でミュンヘン大会の予選があって、そこで勝ってミュンヘンに出たわけですが、僕はその時に大学3年生くらいだったかな…予選を見てあの雰囲気に感動しまして。自分でバスケットをやっている以上は、最終的にはオリンピックに行きたいなという思いだったわけです。ミュンヘンの時は新旧交代があって、僕は大学4年で、就職が住友金属に決まったか決まらないかという感じだったと思います。住友金属には代表選手が5人いたんですが、僕も最終合宿に参加しまして、最終の日に12名が決まることになっていたところ、その中になぜか僕が入ったんですね。でも次の日に…新聞で最終12名を発表することになってたんですけれども、朝5時くらいに起きて新聞を待っていたら、11名しか書いてないんですね。そして翌々日にはその残り1人が、僕じゃなかったんです。
元川:最後の最後で落とされたということですか。それでどのように、精神的に持ち直したんですか。
結城:相当、グレましたね。未成年じゃないですから、酒は飲むわ夜更かしはするわ。ほとんど練習しない状態で関東トーナメントという大学の試合に出ていましたね。関東トーナメントは優勝したのですが、全然うれしくなくて…もうバスケットを辞めようと思ったんですよ。でも、グレてグレて出た結論は、やっぱり下手だから選ばれなかったんだよね、と思ったんです。例えばコイツが絶対いなくちゃダメだというプレーヤーになっていれば、外されることはありえないんですよ。自分は下手で、スポーツは力の世界だから、力のある者が生き残っていくっていう…勝負の世界ってそうですよね。でも、とかくそうではないことも今のアマチュア界にはいくらでもあります。人が選ぶということは、モノサシはその人のモノサシだから。例えば、人が見て判断するスポーツ…フィギュアスケートもそうですよね。そのあたりは非常に微妙な部分で…自分に対するエクスキューズですけれども(笑)。自分にもプライドがありますから。いくら下手だからと思っても、やはりプライドがありますから自分なりに葛藤して、責任を転嫁していました。その一方ではプレーヤーとしてのレベルを上げようと…誰が見ても必要なプレーヤーであれば、どんなことがあろうとも選ばれるだろうと考えていました。
元川:だからレベルを上げないといけないと考えたのですね。
結城:そうです。住友金属に入ってから、一つの大人の社会に入って仲間にも恵まれたというのもあります。仕事を終わってから練習という非常に厳しい環境の中で、仕事もやり、バスケットボールもやりました。これが、スポーツマンとして、今の置かれている日本のアマチュア環境の中で目指すべきものなのかなという感じで。そういう社風というか会社の方針は、わかっていて入ったんです。僕は学校も教育系ではなくて、サラリーマンになろうと思っていましたし、住友金属は非常に自分のイメージが良かったものですから。
元川:どんなお仕事をされていたのですか。
結城:営業です。東京の本社で。32社、担当を持ちまして、ずっと営業をやっていました。住金では、8年目に業務論文を書くんです。昇進の査定ですね。そのころになると、みんな疲れてくるんです。ちょうど30歳くらいの時なので、だいたい住友金属の選手はみんな短命でしたね。10年やった人は僕らの年代ではいないです。どうしても仕事のウエイトが高くなってきますので、やっていける状況ではなくなってくるんですね。
元川:仕事もフルタイムでやって、夕方に練習するんですか。
結城:そうです。7時から練習で、9時半から10時くらいまでやりました。だいたい月水金か火木土、試合があると週に4日とか。毎日やっていたら気が狂ってしまいます(笑)。
元川:その中でレベルアップを目指して、オリンピックにトライしようという思いがあったんですね。
結城:はい。
元川:その後、モントリオールに手が届くことになるわけですが…。
結城:モントリオールに手が届くということは、全日本の中で12名に入ることもさることながら、さらにアジアの予選で勝たなければいけないというもっと大きなハードルがあるわけです。僕はそのアジアのハードルに対して手ごたえがあったんですが、なぜかといいますと、ミュンヘンのオリンピックが終わってその年か翌年に、すぐアジア大会があったんです。
元川:1973年ですね。
結城:アジア大会で日本は4位になって帰ってきたんですよ。その大会前に、アジア大会に行くメンバーと住金が練習試合を何回かやったんですが、全部住金が勝ったんです。僕はもう住金に入っていたんですが、その時の試合は、国内の練習試合では僕が経験した中でも最高にタフなゲームだったですね。肘は飛んでくるわ…ラグビーかバスケットかというような。住金は代表選手が抜けても結構いいプレーヤーがたくさん残っていたので。 それと、アジア大会の翌年は天皇杯とリーグ戦の全部で住金が優勝したので、海外にご褒美旅行をさせてもらったんですね。アジア大会ではフィリピンが優勝したんですが、住金単独で韓国やシンガポール、マレーシアをずっとまわってフィリピンに行って、最後にフィリピンのナショナルチームとフィリピンで1位・2位のチームを相手に3試合やったんです。ナショナルチームというのはアジア大会で優勝したチームですが、それを根こそぎやっつけちゃったんです。これが1974年の2月です。
元川:フィリピンはバスケットボールが強いですよね。
結城:強いですよ、当時はフィリピンと韓国と日本、この御三家でどこが1位になってもおかしくなかったんです。
元川:そのフィリピンをコテンパンにしてしまったということで…。
結城:そうですね。国際大会での手ごたえがあったということと、その1年間で自分がかなり精神的にも肉体的にもタフになってきたのかなという自信もありました。
元川:そういう意味で、「次のオリンピックは行ける」と思ったわけですね。
結城:次はとにかく、1番のプレーヤーになれば…という感じだったですね。モントリオールの前は我々の世代が主力になっていましたから、ミュンヘンの時のように直前で落とされることはないだろうとは考えていましたが、モントリオールオリンピックを目指すスタッフに、僕がミュンヘンの前に落とされた時のコーチがいたんです。実際は複雑な気持ちがあったのですが、自分も精神的に成長したので、後ろを見ないで前を見ようというふうに回路を変えたんですね。僕も自分なりに、プレーヤーとしての自負といいますか、プレーの前提として自分に自信もついてきていましたし。
元川:アジアを突破しなければいけないということもありますよね。
結城:そうです。自分にはそれしかなかったですから。1976年ていうと、26歳か27歳ですよね。年代的に一番タイミングがいいじゃないですか。