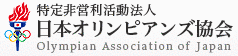- トップページ
- オリンピアンインタビュー
- 第4回 平松純子さん
【オリンピックへの憧れと日本フィギュア界への危機感】
広報スタッフ:平松さんご自身が選手だった時代とは、どんなところが変わってきていますか?
平松:もうね、私たちの時代というのは、今とは違いすぎる。今のような国際交流はまずなかったですよね。そこへきて採点競技ですから、世界の様子がわからないわけですよ。稲田悦子先生が戦前に行かれて、戦争でブランクがあって私たちが戦後育ちの第一期生という形で1957年に派遣になった。今だったら世界選手権だけじゃなくて、国際試合はグランプリもある、しかもノービス(ジュニアの下の年代)から行かせてるでしょう。それが強さにつながってると思うんですけど、私たちの時代は世界選手権ですら毎年行けなくて。あの頃は、映画館で映画の前にニュースがあって、映像が見られるといったらそのくらいなんですよ。私、未だに覚えてるのは、猪谷さんが2位になられた56年のコルチナ(コルチナ・ダンペッツォ大会。猪谷千春氏がスキー・アルペンで銀メダルを獲得した)の時、あの頃からオリンピック選手になりたいって思ったんですよね。当時の映画ニュースで、優勝したテンレー・オルブライトの何秒か…1分もないような映像を見て「あーすごい」と思って、アメリカのロバートソンっていう選手がシットスピンをしてるんですけど、一つのポジションだけで駒が回るような速さで、「すごい」と思ってそれだけを何回も見に行ったんですね、母に連れられて。映画じゃないんですよ、映画の前のニュースのフィギュアのとこだけを見るために。そういう時代ですもの。
広報スタッフ:初めて海外で、日本ではない世界のレベルの選手を生で見られたというのは?
平松:見たのが1957年、今では考えられないことですよね、最初の国際派遣が世界選手権だったっていう。だから、行って「わーすごい」って思って、次に行ったのが60年のオリンピック(スコーバレー大会)ですからね。その間、必死に練習して行ったらまた進んでるわけでしょ?それと、国際審判員になる一つのきっかけだったかなとも思うんですけど、インスブルック(1964年大会)に出るシーズンの夏に大学の夏休みを利用して、カナダで3ヶ月間サマースクールに行ったんですね。カナダの選手や、アメリカからも世界のトップの選手とか金メダルを取った人が来ていて一緒に練習して、そこで日本と外国は違うなと思ったんです。16歳になったらもうバッチテスト(選手の進級テスト)とかのジャッジをさせていた。それから、みんなが自分のロッカーにルールブックを持ってる。まずその二つがすごいと思ったのと、試合とは違って一緒に練習をすることで外国選手との交流ができたことで世界を見れて、外国の連盟はこうなんだという、そこで受けたものが将来につながった。ルールブックっていうのは、競技のバイブルでしょう?ルール通りにすれば点数は取れるわけですよね。選手にジャッジをさせるということは、ルールに基づいてジャッジしないと何が要求されているかがわからないわけですから、そういう意味ではいい教育ですよね、選手の教育。
広報スタッフ:選手の時代に、外国との環境の違い、人材の違いを感じて、日本のフィギュアの環境をもっとよくしていかないといけないということに気づかれたんですね。
平松:それまでは外国との違い、まず練習は氷づくりから、古い話だけどみんな箒で雪を掃いてね、ホースで水を撒いて、そういう製氷だったわけ。ところが外国にはもう機械があるわけでしょ、びっくりすることばかりですよね。私たちは一般営業で滑ってたけど、貸切で滑ってたり。だからもう何もかもが違うという、それは日本が戦争での長いブランクがあって不利なこともありましたけれど、やっぱり国際化をしないと絶対ダメだなと思いましたね。
広報スタッフ:憧れのオリンピックに出て、一番感激されたことというのは?
平松:それはもう憧れ、オリンピックに出たい一心で練習してましたから、すごいうれしかったし、その時私はたまたまね、旗手に選ばれたんですよ。初めての出場で、ただ女性だったから選ばれたと思うんですけど。当時女子が5人で、夏冬通じて女性旗手は初めてで、まだ高校生でしたし、まず出られたっていうことがうれしいのと、すごい光栄なことだということと、あとはもう何て言うのかなあ、そういうところで滑れる、世界の強豪と一緒に滑れるという…オリンピックとはこういうものなんだという、すごい、いい思い出ばっかりですね。
広報スタッフ:競技のほうも、まずそういう場で滑れることの感激が大きいというか。
平松:当時はまだ参加することに意義があったというか…それは一生ついてまわるものですね。未だにやっぱりオリンピックっていうと4年に1回ね、こう、血が騒ぐっていうか、なんか違うんですよね、オリンピックイヤーって。それは冬だけじゃないんですよ、夏のオリンピックに対してもなんか、競技は違うんだけどね、それはわかるのよね、選手の気持ちとか。ああ、こんな気持ち、それは様々な一人ひとり全部違った選手人生というものを歩んできて、その場に臨むんですから。
広報スタッフ:憧れのオリンピックに2回出て、選手を引退する時に何か次の目標をみつけたいというところで、どんなふうに考えたんですか?
平松:1回目のオリンピックに出た時に旗手をさせてもらって、閉会式で当時のブランデージIOC会長、ミスターアマチュアっていう代名詞の方なんですけれど、最後の挨拶で、旗手が回りに並ぶわけ。で、未だに覚えてるけれど、スコーバレーがね、今のような巨大なオリンピックじゃないんですよ。小ぢんまりとしたカリフォルニアとネバダ州の間の谷間でね、各競技全部一堂に集まってコンパクトにやるでしょ。そこでウォルト・ディズニーの演出だったんですけど、雪で真っ白のところに各国のユニフォームがもう色彩豊かで本当に絵みたいでね。
広報スタッフ:映像のようにまだ残っているんですね。
平松:そう。で、夕方だったんですよ、閉会式は。その夕日が当たってるところで「次はインスブルックで会いましょう」っていうブランデージ会長の挨拶があって、その時、絶対私もインスブルックへ行くと、インスブルックまでは頑張ると、絶対もう1回出るんだとものすごく思ったわけです。まだ17歳で高2でしたから、次の目標だったのね、インスブルックが。で、インスブルックに出てそのあとすぐにユニバ(ユニバーシアード大会)があって、そのシーズンで引退。昔のことだから女子は、結婚適齢期とかもあった時代ですから…。
広報スタッフ:じゃあ、その辺はわりと自然に引退を…?
平松:そう、もう自然に…2回オリンピック出るというのが最終目標でしたから。それともちろんできるだけいい成績、前よりは頑張りたいという。もう少しやればもっとうまくなるかなとも思ったんですよ、私は初出場で全日本選手権に初優勝しちゃったんですよね。だから、1回目のオリンピックに行くまではとんとん拍子だったんですね。でも次のオリンピックまでは、若手が出てきて抜かされていく。それまで負けたことがないのが、負ける悔しさとか…いいことばっかりじゃないんだと、このスコーバレーからインスブルックまでの間に自分自身がスポーツ選手として学んだことは多く、ものすごくプラスだったと思いますね。いい時もあるけど、頑張って、打ちのめされて悔しい思いして、そういう人が今までいたんだって、私の後ろにいたんだっていうこととか、この4年間はすごく貴重な4年間でした。技術を鍛えることプラス、精神的にっていうか人間的に成長するっていう意味では。こういうことでスポーツ選手って鍛えられるのかなって。自分への挑戦を積み重ねるっていうか、一番しんどい4年間だったですよ。だからいろんなこと模索して、カナダへも行って。
広報スタッフ:スポーツをやっていて、いいことも辛いことも経験されてきたんですね。あとの人生には、辛かったことというのも生きていると。
平松:やっぱり、何かあった時、あれだけ頑張ったんだって。真夏の陸上トレーニングのきつさとか、毎朝4時起きの学校に行く前の練習とか。まだコンパルソリーっていうのがあって、図形を描く、地味な地味なね。それなんかもう、冬は毎日、手足の感覚がないんですよ。子供の頃からそういう肉体的なしんどさと、それから同じような年頃の子の楽しみはなく過ごして、学校と家とリンクの間だけの行き来と、お正月からも練習とか。でもそれは目的があったから、頑張れるわけですよね。だからやっぱりスポーツっていうのは、すごく人間を鍛えると思いますね。肉体的にも精神的にも。